ジョルジュ・メリエスが映画のなかで、特殊撮影によって人類を月に送り出してから、現在まで続くSF映画の系譜のなかで、『インターステラー』は劇映画として、学術的な視点から、宇宙の神秘に最も深く踏み込んだ作品ではないか。
こういうことを言うと、「映画なんかよりもSF小説の方がはるかにすごいし深いところまでやっているぞ」という人も出てくるかもしれない。だがそれは、小説と映画との制作方法の違いから、仕方のないことだと感じる。
映像作品は、描くものを視覚化しなければならず、読者に文章で長く状況や科学的な理論を説明することもできない。なので、複雑な状況を描き、科学的な考証が高いレベルに達するSF映画が稀少になってしまうというのは必然といえる。
実際には、近年のSF映画を引っ張ってきたのは、宇宙物理の学術知識というよりは、SF小説の存在であったといえるだろう。
そのなかで、オリジナル脚本の『インターステラー』は、映画というフィールドにおいて、SF的な映像表現の未踏部分に足跡を残したことは間違いない。
まず、この業績に素直に驚き、正当に評価することが先決だと考える。
『未知との遭遇』や『コンタクト』、また、なかでもSF映画史上最高作といわれる、スタンリー・キューブリック監督の『2001年宇宙の旅』と本作がよく比較されるのは、人知を超えた存在によって宇宙飛行士が誘導され、人類が新たな領域に導かれていくというプロットが同じものであるからであろう。
本作のハンス・ジマーのスコアに、『2001年宇宙の旅』を彷彿とさせる箇所があることからも、クリストファー・ノーランが、このことに意識的であることは間違いないはずだ。
『2001年宇宙の旅』を簡単におさらいしたい。
冒頭のシーンは延々と、猿の様子が映っている。太古の地球のどこかで、人間の祖先である自然の猿達が、猿として生活を営んでいる、それだけの映像だ。
そこにある日、巨大な石版のような物体「モノリス」が、突如として大地に現れる。
モノリスに触れると、猿達に劇的な知能の向上が起こった。それ以来、彼らは道具を使い始めたのである。そして猿が道具である骨を空中に放り投げると、一気に時代がジャンプし、それが宇宙ステーションを映したカットに重なる。
これは、人知の限りを尽くした宇宙ステーションと一本の骨が、同じ「道具」であるということを示し、これによって、猿が人類に進化したこと、そして人類が文明を発展させてきたこと、その大元をとらえ、さらにそもそものきっかけに、「人を超えた何か」が関与していたことを暗示するのである。これはきわめて高度な演出による洗練された、芸術的にシンボリックな圧倒的シークエンスであり、『2001年宇宙の旅』が映画史上に残る傑作といわれる理由のひとつだ。ノーラン監督に、ここまでの美意識に基づいた演出はできないだろうし、また、ほぼすべての監督が到達できない領域にある優れた表現だろう。
ともあれ、人類はモノリスの導きにより宇宙に進出し、更なる進化を迎え、人という存在を超えることになる。
モノリスは神の啓示なのか。それとも知的生命体の好意なのか。映画のなかでその正体が明かされることはない。
しかしここでは、人が「神」と呼んで崇めてきたものに対する、ある科学的な説明と意味づけがされていることは確かであろう。
『2001年宇宙の旅』は、観客の旧弊な概念を破壊する爆弾であり、新たな発想の扉を開くための鍵でもあったといえる。
『インターステラー』にも、モノリスにあたるような好意的導き手が現れる。
それは、近未来の地球で、砂嵐と作物の不作により滅亡の危機に瀕する人類に、一筋の希望を与えてくれる。土星の近くに現れた「ワームホール」である。ワームホールは「異なる時空への通り道」であり、この出現は、両者間の行き来をスムーズにすることから、他の星への移住の可能性を示していた。
現実的に、地球を含む太陽系には、人類が長期間居住可能な惑星は無いだろうといわれる。
しかし、何光年も離れた惑星に行き着くには、人間はあまりに短命であり、耐えうる宇宙船も無く、燃料も持たないだろう。移住の唯一の道が、他の宇宙空間へつながるというワームホールなのだ。
何故、都合よくそんな穴が出現したのか。そこには、何か高次の存在が関与しているのではないか。
劇中のNASA職員や学者もそのように考え、本棚の近くに現れた、座標を示すデータの発見という、まさに人知を超えた理由によって、極秘のNASA研究所の場所を探し当てたという、マシュー・マコノヒーが演じる元宇宙飛行士クーパーを、人類の存亡を賭けたミッションのパイロットにするというところからも、彼らが奇跡の存在を信じざるを得ないような状況が、宇宙空間に起こっているということが分かるのである。
人類が遠く離れた星間を航行しようとすると、猿が進化し宇宙空間にロケットを飛ばすのと同じくらいの、爆発的な知能や技術の向上が必要かもしれない。そのために、やはり何か神のような導きを必要とするのだろう。
それでは、『インターステラー』のストーリーに注目していこう。
人類の存亡を賭け、「人類移住」、または「種の存続」を目的とした「ラザロ計画」が実行された。
ラザロとは、新約聖書において、キリストが奇跡によって死から復活させた男の名前だ。この時点で、すでにワームホールを通過した3つの先発隊が、到達したそれぞれ3つの惑星からの信号を発信している。今回の任務は、その3つの惑星を評価し、移住の先鞭をつけるか、凍結された受精卵を使用し、新たな人類の歴史をスタートさせなければならない。
信号を受けた惑星で滅びに向かう人類を再生させる。これが「ラザロ」という単語に込められたねがいであろう。
宇宙飛行士達は、優秀な人口知能を有したサポート機械「TARS」らと共に、遠心力によって内部の重力を作り出す宇宙船・エンデュアランス号で宇宙空間へ飛び立つ。
「エンデュアランス」とは、二十世紀のはじめに南極探検に行ったイギリスの探検隊が、難破し17ヶ月漂流するも、不断の努力によって奇跡的に生還したという、「不屈の魂」を表す帆船の名前でもある。
さらに、物理学者のブランド教授は、自分の娘を含む宇宙飛行士達に、「穏やかな夜に身を任せるな 老いても怒りを燃やせ、終わりゆく日に…」というディラン・トマスの詩を引用し勇気付ける。
滅び行く運命に抗うような、これら一連の表現は、重複された同じ意味づけがされている。ここにクリストファー・ノーラン監督の、他の映画監督には無い、きわめて粘着的な作家性が見て取れる。
時空の裂け目であるワームホールの美しくミステリアスなデザインは、制作者でもある物理学者キップ・ソーン(『コンタクト』原作にもワームホールの件で協力している)の監修のもと、アインシュタインの相対性理論を用いてシミュレーションされているという。立体的な球面の穴が、鏡面のように宇宙の星の光を反射する姿は、いままでに見たことがないような宇宙の神秘を感じるものになっている。
ワームホールというものが存在するという概念は、1935年にアインシュタインらが論文にて発表している。
もしワームホールを開くことに成功したとしても、宇宙船や人体が通過できるほどの大きさではなく、また長時間は存在できないだろうといわれている。これにはやはり、人類の知能を超えた技術が必要になるのである。
宇宙飛行士達が到達した空間は、巨大なブラックホール「ガルガンチュア」にも近い、他の惑星系であった。ちなみに「ガルガンチュア」という名称は、フランスの民話として伝わる巨人の名であり、ルネサンス期の作家フランソワ・ラブレーの奔放な文学「ガルガンチュア物語」がその名を有名にし、現代に伝えている。ラブレーの作中のガルガンチュアは巨人族の王であり、その望外の巨大さと得体の知れなさは、この巨大なブラックホールを表すのに適当だろう。
彼ら宇宙飛行士達は、限りある時間と燃料を気にしながら、様々な条件を加味し優先度の高い星から優先的に探索していく。
この道程は、旧約聖書を逆から追っているようにも思える。
最初の、水と波の惑星は「ノアの箱舟」を指し、マン博士と出会い裏切られる氷の惑星では、「カインとアベルの兄弟殺し」を暗示させ、最後の惑星では「アダムとイヴの楽園」を彷彿とさせる。
宇宙を題材にした作品だが、民間伝承や宗教のモチーフが用いられていることが、作品にある種の神話的美しさを与えているといえるだろう。
ひとつ目の星は、ガルガンチュアのもたらす重力の影響で時間の進み方が極端に早い、水に覆われた星だった。アインシュタインの「一般相対性理論」では、重力が時空を歪ませるため、ブラックホール周辺の重力場では時間の進みが遅くなるという。
エンデュアランス号の乗組員三名は、小型探索船レインジャーに乗り換え、惑星探査を開始する。
当初は有望と思われた惑星だったが、陸地が確認できないことと、津波の発生によって発信者がすでに事故死していたこと、また乗組員をひとり失ったことで、到底、人類の居住には適さないことが分かった。
探査船レインジャーが水をかぶるトラブルによって小一時間足止めされ、やっとのことでエンデュアランス号に帰還すると、そこで待っていた乗組員はだいぶ老け込んでいた。この探索だけで、23年も経っていたのである。
宇宙飛行士クーパーが、地球からワームホールを経由し受信された電波によって、家族からの交信を確認すると、自分の父親が死んでいることや、自分と同世代になって結婚した息子の姿、娘のマーフが成長し物理学者になっていることなど、衝撃的な知らせが次々に伝えられる。この絶望感。宇宙への恐怖。これを具体的にヴィジュアルで見せられると、その凄まじい理不尽に圧倒されてしまう。
まあそもそも、ブラックホール周辺の惑星に移住しようと計画すること自体がちょっとおかしいのだが、本作ではブラックホールが非常に重要な役割を果たしているので、そのあたりは問うまい。ちなみに、ブラックホールについての説明は後述する。
カメオ出演であるマット・デイモンが演じるマン博士が登場する、氷に覆われた第二の惑星で、宇宙飛行士達はこれ以上のトラブルに見舞われる。
信号を送っていたマンは、地表が存在せず居住に適さない星から脱出の手段が絶たれ、孤独に死ななければならない運命であった。だがその恐怖に耐えられなくなった彼は、信号を送り、他の宇宙船を呼び寄せ、人類の貴重な時間と機会を浪費させるような選択をしてしまう。
卓越した頭脳を持ちながら、狂気に苛まれ理性を失ったマン博士は、助けに来たクーパー達を騙し、乗組員をひとり殺害し証拠隠滅を図る。さらにエンデュアランス号を奪おうとするが、セキュリティを突破できず、小型探査船のドッキングに失敗し、宇宙空間へ吹き飛んでしまった。
マンは、自分自身が強く提唱した星に旅立つ際に、リスクを十分覚悟していたはずだ。人類のために危険をかえりみず、死を覚悟してミッションに参加した、理想に燃える立派な男だったはずだ。
自説が目指すところが間違っていれば、研究に費やした時間全てを無駄にしてしまうというのが、正誤によってのみ価値が決まる学者の宿命である。解けない難問のプレッシャーに数十年さらされることで発狂する学者も実際に存在する。
ニュートンやアインシュタインのように、偉大な発見をして人類の発展に貢献する人物がいる裏で、学問のため人生を犠牲にする学者達がいる。マン博士は、その代表として描かれた人物であろう。この苦悩、この心の闇の果てに現れた狂気の存在無くして、人類の輝かしい前進も無いのだ。
マン博士という人間を描くことで、『インターステラー』は、多くのSF作品を凌駕する、優れた倫理性と、優しいまなざしを獲得しているといえる。
氷の惑星で格闘するふたりを超ロングで捉えたショットは、実際にアイスランドの氷原でロケされた、本物の映像である。映画ファンであれば、その巨大な大地のおそろしい実在感に、『大いなる西部』を思い出す箇所であろう。
ここで気付かされるのは、本作は宇宙探検映画でありながら、アメリカ入植者による西部開拓の精神もまた、根底にあるということだ。
もちろん、西部開拓というのは先住民の土地を奪い征服するという、負の側面が多いことは事実だ。しかし『大いなる西部』は、旧弊な西部劇の価値観とは一味違う作品になっている。
グレゴリー・ペックが演じる『大いなる西部』の主人公は、東部から西部に移住しにきた男である。彼は東部の教育を受け、比較的進歩的な考えを持っており、封建的な西部のしきたりや人間達に戸惑い、軋轢を起こしてしまう。
その土地では、ふたつの農園主が水源を争っており、それぞれが貴重な水を独り占めしようとしている。
主人公は、自分と敵対する勢力も含め、水をそれぞれに分けるよう尽力する。目先の利益でなく、大局的で公平な目線で、多くの人が幸せになる道を取ろうとする。だからこそ、彼は主人公たる資格があるのだ。
『インターステラー』では、マン博士が 「人間は、家族などの単位でしか愛情を持てない」 と言って、自分の行為を正当化しようとする。
しかし実際は、乗組員殺害や証拠隠滅など、人類存続と関係がない、自らの保身のための行動に走っていることは明白だ。
対してクーパーは、「俺は全ての家族を守りたい」と言う。家族など自分の身近な存在を大事に思う気持ちを拠り所に、そこから大勢の他者の気持ちを想像する。小さな世界観しか持てない一個の人間は、おそらくそのようにしてしか、他者の身になって考えることはできない。そして、特定の人間への深い愛情があってこそ、自分を犠牲にする判断ができるということが言いたいのだろう。
アン・ハサウェイ演じるアメリア飛行士は、「愛には意味がある」と言った。愛があるからこそ、自分を捨てて道を切り拓くことができる。偉大な任務を成し遂げる背景には、大いなる愛こそが必要であり、他者への愛が生み出す理性こそが、『大いなる西部』のように、利己主義に勝利することになる。
様々なモチーフを繰り返しながらの、このような大上段からの主張は、やはりクリストファー・ノーラン監督の粘着性と生真面目さからきているだろうが、今回はとくに、きわめて率直かつ泥臭くテーマを表現していることが分かる。
マン博士の暴走によってエンデュアランス号は部分的に破壊されるも、引き続いての航行は可能だった。しかし、燃料と酸素が消費され、地球へと帰還する能力が失われたため、地球に帰ることを断念し、生き残ったクーパーとアメリアは、エドマンズ博士が候補に入れた星に向かい、プランB、つまり既存の人類を救うためでなく、現地で新たに人間を人口繁殖させる計画を実行する道を選ぶことを余儀なくされる。
クーパーは、エドマンズの星までのエネルギーを確保するため、ブラックホールの回転力を利用することを思いつく。
ブラックホールは4種類あるといわれているが、現在の研究では、実在するものはそのなかの2つだけだといわれている。質量だけを持つシュバルツシルト・ブラックホールと、質量を持って回転するカー・ブラックホールである。
エネルギーが取り出せるのは、回転するカー・ブラックホールであることから、劇中に登場するブラックホール「ガルガンチュア」は、カー・ブラックホールであると考えられる。
それを前提にその構造を説明していきたい。
カー・ブラックホールは、シュバルツシルト・ブラックホールと比較すると、複雑怪奇である。
まず外側には「エルゴ球」という空間が存在する。これはブラックホールの回転にしたがって空間が引きずられている領域で、赤道上がふくらんでいる。
ブラックホール中心にあるのは時空が曲がった「特異点」だということは、実在の数学者ロジャー・ペンローズが唱えた、数学を利用した「特異点定理」によって証明されている。
だが、ブラックホールの外側からは特異点は観測できない。 ブラックホールの中心をのぞき込むには、ブラックホールの表面の重力場を超えなければならず、超えてしまうと強力な重力にとらえられてしまうからである。
特異点を確認できないということは、そこでどんな事が起こっているかも分からない。どんなことが起こるか分からない境界を、事象の確認できる限界であることから、「事象の地平面(地平線)」と呼ぶ。
カー・ブラックホールでは、その領域が2段階あると考えられている。「外部地平面」と「内部地平面」だ。
外部地平面は、光すら飲み込む重力場である。しかし、ブラックホールの回転力によって、そのさらに内部では、光がドーナツ状の円周を描き停滞する。この輪の内部奥深くに特異点がある。
ブラックホール周辺の領域「エルゴ球」に進入し、ブラックホール自身の回転を利用することで推進力を獲得するエンデュアランス号。
その途中で、ブラックホール内部を探査するため、TARSが乗った着陸船ランダーは切り離され、ブラックホールの引力に吸い込まれていく。
続いて、アメリアの目を盗んだクーパーは、自身の乗ったレインジャーを切り離し、ランダーの後からガルガンチュアに突入する。エドマンズの惑星にエンデュアランスが到達するには、エルゴ球内部でのさらなるエネルギー獲得が必要だったことを、クーパーは土壇場まで黙っていた。
ペンローズの提唱したエネルギー獲得の方法とは、ブラックホール周辺のエルゴ球の領域に物体を侵入させた後に、その物体を分裂させ、一方をブラックホールの回転の逆方向に向かって落下させると、もう一方がエネルギーを得て飛び出すという理論に基づいたものだ。
ペンローズは分かり易く、「ゴミ箱のゴミをブラックホールに捨てることでエネルギーが取り出せる」というように表現している。
この説に似た話として、スティーヴン・ホーキング博士の70年代の研究がある。
量子力学の観点から、生成された光子(ミクロレベルの光の量子)の対の片方がブラックホールに飲み込まれたときに、もう片方が飛び出してくるという予想だ。だからブラックホールを外から眺めると、ブラックホール自体が光っているように見えるのだという。
劇中で、光すら飲み込んでしまうはずのブラックホールが発光していたのは、この説が基になっていると考えられる。
ブラックホール最深部の特異点で、何が起こるか分からないということは、現代科学においてその存在は「幽霊」と同義であるというようにいわれる。
人類は、多くの研究者達の努力によって、自然の謎をひとつひとつ解明してきた。それ以前、説明のつかない事象は、呪術や心霊などの領域であるとされてきたのである。ニュートン力学を確立したアイザック・ニュートンでさえも、オカルト的研究に熱心であったことは有名だ。
『インターステラー』冒頭では、クーパーの娘マーフが、本棚の裏に幽霊がいるのではないかと家族に訴え、それに対しクーパーは、「突きつめて考えろ」とアドバイスする。
分からない事象は幽霊と同じだが、それを理論的に理解し証明するという姿勢が、人類を進歩させる。そして、この冒頭の問いかけは、映画の終盤になって解決することになる。
TARSとクーパーのガルガンチュア探査の目的は、あらゆるものを吸い込んだブラックホールの中心、特異点の観測データ採取にあった。何故このデータが重要なのだろうか。
地球の人々を他の惑星に移住させるには、大規模な移動手段が不可欠である。しかし、現在の宇宙船の推進方法では、莫大な費用をかけて乗組員数名を打ち上げるのがやっとなのだ。
ここで役に立つのは、「反重力推進」という、自然界の重力を制御し、ロケット打ち上げなどに頼らない宇宙航行の概念である。
反重力は、重力をコントロールする技術のことで、現在の物理学では実現が不可能であるといわれている。
しかし、実際にNASAは反重力を用いた安価な宇宙船の開発に資金を出していたという事実があり、宇宙探査の抜本的な改革を行おうとしていたことは確かだ。
この「反重力」を可能にするためには、いまだ完全には解明されていない「重力」という幽霊の正体を明らかにしなければならない。
アイザック・ニュートンが発見した「万有引力の法則」は、地球の重力を説明した重要な理論で、いまも様々な分野で利用されている考えだ。
アルベルト・アインシュタインの「一般相対性理論」は、その重力の概念をさらに深くとらえた。
彼は宇宙を、「たて、よこ、奥行き」の三次元の空間ととらえ、そこに「時間」軸を加えた四次元で構成された「時空の織物」だと考え、天体の運動をより正しく説明することに成功した。
この発見によって、今まで分からなかった重力の秘密が解明できたように思われた。
しかし相対性理論のみでは、説明の出来ない事柄もある。それはミクロの世界、量子力学の事象である。そこでは、アインシュタインが唱えたような、秩序立った理論が通用しないのだ。
量子力学との矛盾を解消し、重力など自然界に存在する力を解明する、宇宙の万物を説明する理論、「統一理論」の完成は、現在の物理学者の夢見る到達点であるといえよう。その研究の道なかばで、アインシュタインは亡くなっている。
これら謎を解き明かすためには、宇宙を根本的なところから考えていかなければならない。
宇宙のそもそもの始まりは、約138億年前のビッグバンという巨大な爆発が原因であったといわれる。だが、何故このような数字を導き出すことが可能なのだろうか。
我々のいる宇宙は、数々の銀河によって形づくられている。
「天の川銀河」ひとつだけでも、約2000億の恒星が存在し、そのうちの数百億個には惑星系があると考えられている。地球が含まれる太陽系はそのひとつに過ぎない。
天文学者エドウィン・ハッブルが望遠鏡で宇宙を観測すると、「複数の銀河が地球からだんだん遠ざかっている」ことを発見した。そして、遠い銀河ほど速いスピードで遠ざかっていることも分かった。
銀河が「遠ざかっている」ということは、昔はもっと密の状態にあったという予測が成り立つ。
そのまま時間を逆に回転させ、どんどんさかのぼると、もともとは一点に収まるのではないかという考えが生まれる。それが、「特異点」と呼ばれる、極小の、しかし超大質量の物体である。
高い質量にある「特異点」が、あるとき巨大な爆発を起こし、周囲に拡散していくことで宇宙の歴史が始まり、そして現在も、多くの銀河はそれぞれ拡散を続けている。つまり、我々がいるこの世界は、ビッグバンという、いまだ宇宙創成の爆発の途中にあると考えられる。これがよくいわれる、「宇宙は広がり続けている」という言葉の意味である。
だが、そもそものはじまり、「特異点」とは結局どのようなものだったのかについては、今現在も謎に包まれたままだ。
前述したように、ブラックホールのなかにも「特異点」があると考えられている。
ブラックホールの質量は、確認されている天の川銀河のブラックホールが太陽の400万倍、M78と呼ばれる銀河では、太陽の60億倍の質量を持っていると予測されている。
強力な重力であらゆるものを飲み込んでいく内向きの力を持つブラックホール中心の特異点の密度は凄まじく高質量であり、外向きの力を持つビッグバンの逆のモデルだと考えることができる。
ブラックホールの最深部に存在するだろう「特異点」の観測が出来さえすれば、ビッグバンの特異点の予想が可能となり、宇宙誕生の謎が解けるかもしれない。
X線などによってブラックホール研究は進んでいるものの、事象の地平面を超えることができない人類の現状は、研究データが足りず、理論物理による予想によって宇宙の謎に迫らざるを得ない部分が大きい。
だが、理論物理学者の代表的存在であるアインシュタインの相対性理論に基づいた計算式で宇宙創世までの時間を追っていくと、宇宙の創生については、ビッグバン直後までしか遡れず、爆発の瞬間では方程式が破綻してしまうのである。このままでは、相対性理論は間違っていたことになってしまう。
そこに光明を与えたのが、「超ひも理論(超弦理論)」という、今まで学会で、全く重きを置かれていなかった考え方だ。
世界を構成する物質の最小単位は、従来考えられてきたような、粒子と呼ばれる点状のものではなく、超ミクロの、輪を描き振動するひものようなエネルギー体ではないかという考え方だ。
これを前提に、相対性理論を用いて特異点の計算をすると、破綻が生じなかった。そればかりでなく、特異点やミクロの世界を、相対性理論と結びつけることが可能になってくるデータが次々に発見された。
この考え方が正しいのならば、「統一理論」完成に、人類は迫りつつあるといえるかもしれない。
「超ひも理論」は、理論的に宇宙の謎を説明出来るというだけで、実際にそれが正しいかは、まだ実証されていない。だが、科学者の多くが、この理論が最も有望であるとしていることは事実だ。これが正しいと仮定して、現在では多くの学者が様々な新しい理論を打ち立てている。
「超ひも理論」をさらに発展した考え方が「M理論」である。これは、宇宙が11次元で成り立っている膜のようなものであるという。「ブレーン・ワールド」(膜宇宙)という最新の宇宙観を持ったものだ。
『インターステラー』劇中にも、キップ・ソーンが黒板に書いたもののなかに、膜宇宙に関する記述があることから、作品の宇宙観にもこれが採用されていることが分かる。
物理学の世界では、自然界に存在する全ての力を、できるだけシンプルに統一できないかと、試行錯誤されてきた。
その結果、量子力学というミクロの世界を含め、自然界の全ての力を、4つにまで減らすことに成功した。「電磁気力」(光、電気、磁力)、「強い力」(原子の内部で陽子と中性子を結びつける)、「弱い力」(放射性崩壊)、そして「重力」である。
このなかで重力は、圧倒的に弱い力だということが分かっている。地球という巨大で大質量の物体が持つ重力であっても、その大地に引きつけられている、比べられないくらい小さな人間が、立ち上がったりジャンプしたり、重力に対抗することが可能なのだ。
他の力に比べ、何故、重力はこんなに弱いのだろうか?
理論物理学者リサ・ランドールは、重力がひとつの宇宙に閉じ込められることがなく、全ての次元へ広がっているのではないかという仮説を打ち立て、ブレーン・ワールドの信憑性を高めた。
さらにこれを基に、ビッグバンとは、複数の膜宇宙同士がぶつかったときの衝撃であるという意見も出始めた。
このような話が真実だとするなら、まさに宇宙の秘密を解くことと、重力の秘密を明らかにすることがつながったことになる。
実際に観測されていないこのような理論は、人間の頭の中に存在する世界だ。「ブレーン・ワールド」(膜宇宙)は「ブレイン・ワールド」(脳宇宙)であるともいえるだろう。
これを視覚的に描こうと試行錯誤したのが、ガルガンチュア内部の幻想的なデザインだ。
このような抽象的な宇宙観を、映画で表現しようとしたクリストファー・ノーラン監督の壮大な試みは、映画芸術の枠を一部において超えて、いささか異常とさえいえるだろう。それは、『2001年宇宙の旅』の同様なシーンを髣髴とさせると同時に、その挑戦的姿勢までも思い出させる。
ガルガンチュアに飛び込んだクーパーが目覚めると、そこは「宇宙の図書館」のような空間で、上下前後左右に書物が並んでいた。
よくよく観察すると、その先には自分の娘マーフや過去の自分が見える。
ブラックホールの中心に飛び込んだら、いつしかクーパーは自宅の本棚の裏の、薄い空間にいたのだ。これは一体、どういうことなのだろうか。そして、おそらくこの箇所が、多くの観客から「『インターステラー』がご都合主義のトンデモ作品だ」とする意見が出る理由でもあるだろう。
クーパーは、宇宙へ行こうとしている過去の自分を止めようと本棚の裏から叫ぶが、過去の自分やマーフには全く聴こえないようだ。
彼のいる場所は、過去の自分とは異なる次元であり、他のブレーンワールドである。前述したとおり、複数のブレーンワールドが存在するという概念が正しいのならば、その間を通過できる力は、「重力」のみとなるはずだ。
彼は、本を落下させるなど、自宅の重力をコントロールすることで、マーフに情報を伝えていく。
さらに、彼が無数に並ぶ本棚達を横目に移動していくと、時間を移動できるということも分かった。
成長し物理学者になったマーフに、腕時計の針を動かすことで、特異点のデータを伝えたクーパー。これによってマーフは、現代の我々の科学を超越し、重力の謎を解き明かすことに成功したのだ。
それにしても、この時間を好き勝手に移動し、重力を思い通りにコントロールできる、とっても便利な空間とは何なのだろうか。この謎について考えてみたい。
余剰次元というのは、コンパクト化されており、我々の次元からは、通常観測できないというのが、カルーザ=クライン理論である。
リサ・ランドールは、「見ることの出来ない余剰次元は、あなたの家のキッチンにもあり得る」と言った。そう、本棚の裏のわずかな隙間にもだ。
我々が現在この瞬間にいる世界は「三次元」である。そして、そこに時間軸を加えた「四次元」は、概念として理解できるものだ。
しかし、この瞬間三次元にいる我々は、四次元をコントロールすることができない。
「たて、よこ、奥行き」から作られる立体世界が三次元のモデルであることはすでに述べたが、四次元のモデルとはどのようなものだろうか。それが「四次元立方体」(超立方体)と呼ばれるものだ。
点と点を結べばひとつの線分が表すことができる。これが一次元の世界である。線分同士をふたつの線で結ぶと、二次元の正方形、すなわち面が出来上がる。ふたつの面と面を、4つの面で結ぶと、立体たる正立方体となる。
この流れで行くと、四次元立方体は、ふたつの立方体を六つの立方体でつなげばいいことになる。しかしこのモデルの理解は困難である。
その抽象的な概念を、映画の立体技術さえ使わず、あえて二次元で表現しようという試みが『インターステラー』で成されている。
それが、本棚の裏の映像が連なり、それが各々の時間を指している描写だ。
回転するカー・ブラックホールの特徴のひとつに、特異点がリング状の領域になっていることが挙げられる。
ブラックホール研究の第一人者ロイ・カーは、相対性理論を基に計算を進めた結果、回転するブラックホールのリング状の特異点には、ブラックホールの出口、「ホワイトホール」があるのではと考えた。このホワイトホールは、「カー・ワームホール」と呼ばれる。
クーパーがガルガンチュアから脱出することができ、全く離れた他の宇宙に移動できたのは、「カー・ワームホール」の構造を利用したものだということが分かる。
さらにクーパーが飛ばされた場所は、人類の行動範囲内であり、マーフの寿命が尽きるまでにギリギリ間に合ったことと併せ考えると、カー・ワームホールの出口は、作為的に用意されたものであると考えるのが自然だ。
このクーパーの時間と空間の移動は、ブラックホール特異点が、タイムマシンとして利用することができるという可能性を示している。
じつは、『インターステラー』の科学考証を行ったキップ・ソーンは、学生と共同でワームホールを利用したタイムマシンについての論文を書いている。
人類の導き手は、ブラックホールの内部構造を利用したタイムマシンを作り、クーパーらをその場所へ誘導していた。
しかし、クーパーはタイムマシンの中で、自分達を導いたのは、自分達自身であったと言っている。タイムマシンのクーパーが、過去のクーパーにヒントを与えていたのだ。
そして、自分がマーフに伝えた特異点データで重力を克服した、遠い遠い先の未来の人々が、未来の技術を駆使し、過去の宇宙にワームホールを作り、ブラックホール内部の特異点を利用したタイムマシンを、クーパーのために用意するということを可能にしたのだろう。
時空を超えたタイムマシンは、出口の時空を自由に設定できるのと同様、本棚の裏の薄い空間とブラックホールをつなげ、干渉させるようなこともできるはずだ。
ひとつ残されたのは、いわゆる「鶏が先か、卵が先か」という問題である。
クーパーが特異点データを送らなければ、未来人の発展はなかった。未来人がワームホールをひらかなければ、クーパーがタイムマシンに到達することはなかった。双方の現象が、互いの現象が存在しなければ成り立たないのだ。これは明らかな矛盾点だろう。
この矛盾を解消できるようなアイディアがあるとすれば、量子力学におけるコペンハーゲン解釈から発展したパラレルワールドの概念を適用できるかもしれない(「『ミッション:8ミニッツ』 シュレーディンガーの猫とクラウド・ゲートの謎を追う」の記事を参照)。
他に考えられるとすれば、次元を超越した未来人にとって、時間の一方的な流れは無効化されているため、自分達自身の存在すら自分で作りだせることが可能になるような時間感覚を有しているということだ。
ここまでくると、三次元の世界で生きている我々には全く理解できない領域の話になってしまうが、そもそも次元を超越していない我々に、時間のコントロールの概念を想像できないのも、道理といえば道理かもしれない。
よく「タイムマシンで過去を大きく変えてはいけない」と言われる。このように過去を変えれば未来も変わってしまうわけで、クーパーの助けがなく、何らかの方法で進化した未来人は、自分達の状況を改善するために、過去の歴史に関与し、自分達の進化を自分達で効率化しているのかもしれない。そのひとつが、クーパーをガルガンチュアのタイムマシンに搭乗させることであったということではないだろうか。
ともあれ、アメリアをエドマンズの星に到達させたクーパーは、おそらく未来人によるはからいで、マーフに特異点観測データを送ることに成功し、また「必ず戻ってくる」というマーフとの約束をも果たすという、はなれ業を達成したことになる。
マーフの理論によって、反重力システムを利用した、巨大なスペースコロニーが建造され、人類は地球の砂嵐から解放された。
アメリアは遠い未来でエドマンズの星にいる。
未来人が作ったワームホールは役目を終え消滅していることから、クーパーは半永久的に動く、反重力推進の宇宙船に乗って、「愛のために」途方もない未来まで宇宙空間を進み続けるだろう。
ブレーンワールドを基にした考えの中に、宇宙の始まりであるビッグバンは、隣合う膜宇宙同士が衝突したのではというものがあることは、すでに述べた。
これが事実であるなら、再度の衝突によって宇宙そのものが消滅することもあるだろう。このような宇宙の消滅から自分自身を救うためには、次元の超越が必要であり、時間をコントロールする技術が不可欠だ。
もしそれが可能ならば、種の滅亡はなくなることになる。これが人類の目指すべきひとつの目標であろう。
しかし、それで進化は終わるわけでなく、次はさらに6次元、7次元の支配へと、人類は手を伸ばすかもしれない。
M理論によると、とりあえず宇宙は11次元まで存在するようなので、当分、知的に退屈することはないだろう。
『2001年宇宙の旅』では、人間を超越した存在が人類を導いていたのに対し、『インターステラー』では、次元を超越し時間を操る、神に近しい存在は、進化した人間自身であったということを言っている。
神に全てをゆだね、運命に身を任せ滅びていくのでなく、自らが神へと進化する能動性を見せるという気概を見せなければならないと主張している。
それが、「穏やかな夜に身を任せるな 老いても怒りを燃やせ、終わりゆく日に…」というディラン・トマスの詩として、しつこく強く表現されている。
『インターステラー』を観ることで、宇宙に興味を持って、宇宙飛行士や技術者、研究者を志す子供は、間違いなく出てくるはずだ。本作は、そのような未踏の地を目指す者への応援であり、人間のなかにあるエンデュアランス「不屈の魂」を見せてくれるものなのだ。
その姿勢は、クリストファー・ノーラン監督自身の、映画への関わり方にも見て取れる。
CGを極力使用せず、巨費を投じ手間をかけてまで実写にこだわり、アナログフィルムでの撮影や上映が最良であると信じ、狂気のように映画を作ること。その強い信念は、光と影の圧倒的に実在感のある映像になって、確かに画面からひしひしと伝わってくるような感覚がある。
個人的にも、クリストファー・ノーランは、演出において万能的ではないし、バランスのとれた能力を持った映画監督ではないと思う。
受け手の呼吸を意識したリズムや、洗練された省略、役者の観念的な撮り方など、従来「映画の粋(いき)」として楽しまれてきたような感覚がきわめて希薄なのは、彼の作品を観ていけば明らかである。そして、感覚よりも理屈で全て映画が理解できると思っているような、鈍重さと傲慢さをも感じるのである。鑑賞経験が豊かな映画ファンのなかで、拒否反応を示してしまう人がいるのも、うなずけるところだ。
私もこのような理由から、個人的にノーラン監督の作品には一定の距離を置いて楽しんできたのだが、『インセプション』を観て以来、評価が一変した。この一作のみがものすごいということでなく、彼に対して考え違いをしてきたことに気づいたのだ。
なるほど、ノーラン監督は、従来の映画の機微や洗練からは無縁かもしれない。だが、「時間の流れの異なる夢の階層」という、きわめて面倒くさい表現を、観客に納得させつつエンターテインメントに結びつけることに成功しているのである。
ノーランには、並の映画監督にはない、「きわめてややこしい状況をしっかりと観客に説明する」という謎の強い信念と、しつこい粘着性がある。これは紛れもなく才能であり、独創的な作家性である。
『メメント』や『プレステージ』、『インセプション』など、通常の監督であれば、「これは映像作品に向いてない」とか、「こんな複雑な説明は観客に理解されないだろう」と、考えついたとしてもすぐに断念するような、こんがらがったあれこれを、わざわざ自ら設定し、それでも観客を楽しませてきたノーラン監督は、考えてみれば、今回のようなややこしい概念をきわめて分かり易く大衆的なSF映画として作り上げる人材として、まさに適任だったといえるのではないだろうか。
本作は、同業である映画監督達による絶賛の声が多く聞かれる。これは、容易に達成できない、難度の高い表現がなされていることを意味している。
ノーラン監督が現在、ハリウッドでヒットメイカーとして最も評価されるひとりであること、彼がSF映画制作について情熱を燃やしていたこと、そして彼の適性がSF作品にマッチしていたことなど、様々な好条件が重なったことで、SF映画史に新しい一歩を刻みつつ、ちょっとクドいけれども、とてつもなく分かり易い『インターステラー』が完成したといえるだろう。


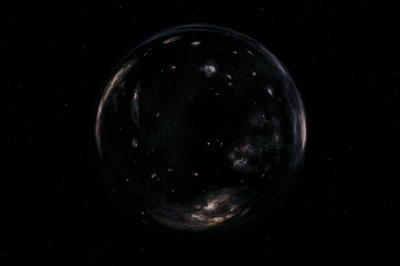





10 thoughts on “『インターステラー』視覚化せよ!ブレーンワールド”